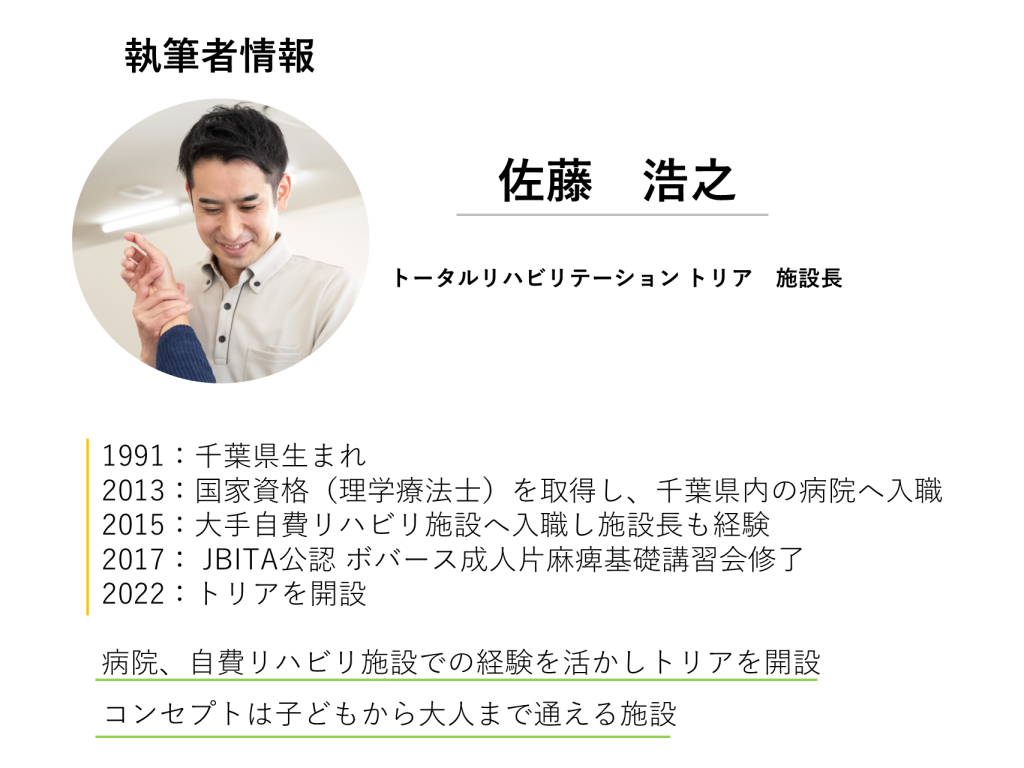トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ
TEL.047-711-3007
豆知識
【脳卒中 筋肉の硬さの正体は⁉】短縮 筋緊張
脳卒中、脳血管疾患を発症された方は、筋肉の硬さで悩まれているのではないでしょうか。
脳卒中を発症された初期は筋緊張は低下し、筋肉が柔らく力が入らない身体状態になりますが、経過とともに筋緊張が高まり筋肉に張りが戻ってきます。
この筋緊張が高まり始める事と同時に、筋緊張コントロールが難しい事が原因で筋肉の硬さが生じてきます。
筋肉の硬さの原因は大きく2つ
・筋肉の短縮
・筋肉の筋緊張が高い
両者とも筋肉を触れば硬いですが、原因は異なります。
今回の記事では、2つの原因とリハビリのポイントについて説明していきます。
こちらの動画では脳卒中後の筋肉の硬さを、短縮、筋緊張、出力の3つから解説しています。
本記事と合わせてご視聴いただくことで、より筋肉の硬さの原因、違いについて分かります。
こちらの動画は感覚情報から姿勢や運動を調整する自主リハビリです
正しい感覚情報を促すことで、筋緊張のコントロールを促すことが可能です。
〇筋肉の短縮とは
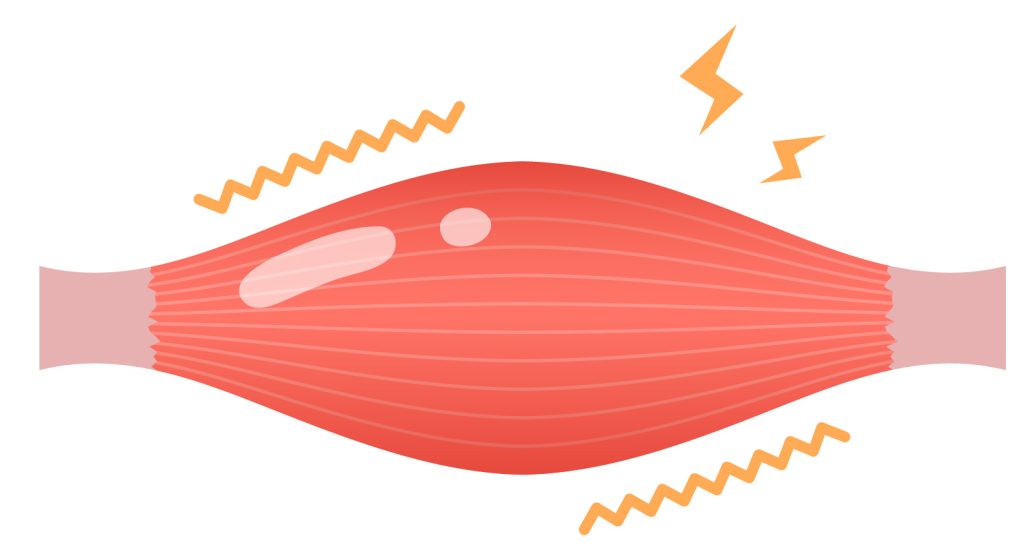
筋肉の短縮とは言葉の通り、筋肉が短く縮んでいる状態を表します。
筋肉は本来ゴムの様な性質で、伸びたり縮んだりしますが麻痺の影響などで動かしづらく、伸び縮みが少なくなると一定の長さに保たれてしまい短縮し硬くなります。
筋肉が短縮しやすくなる理由には以下が挙げられます。
1. 長期間の不動・同じ姿勢
原因:長時間座っている、あるいはベッドで寝たきりなどで、関節が一定の角度に固定された状態が続くと、筋肉がその状態に適応して短縮します。
2. 筋肉の使いすぎ(過緊張)
原因:特定の筋肉を繰り返し使いすぎると、その筋が緊張状態になり、リラックスできずに徐々に短縮することがあります。
3. 柔軟性不足・ストレッチ不足
原因:定期的にストレッチや可動域運動をしないと、筋肉が徐々に硬くなり、短縮します。
4. 損傷後の拘縮
原因:骨折や筋・腱の損傷後に、安静期間が長すぎると、瘢痕(はんこん)や線維化により筋肉が短縮します。
5. 神経系の異常
原因:脳卒中や脊髄損傷などによる神経系の障害では、筋緊張の異常(痙縮)によって筋が短縮します。
6. 加齢
原因:年齢とともに筋繊維が減少・線維化し、弾力性や伸張性が失われることで短縮傾向になります。
7. 精神的要因(ストレス)
原因:ストレスや不安により筋緊張が高まり、それが慢性化して筋肉が短縮することがあります。
1や2の姿勢や筋肉の使いすぎというのは、脳卒中により体を動かせない、動かしづらいことで長時間同じ姿勢であることを考えると大きな原因となることが考えられます。
今回は7つの原因を挙げていますが、どれか1つだけではなく複合的に影響しているので改善できる項目から取り組んでいくことが必要です。
では短縮を軽減させるためには、まずはリハビリで筋肉を活動させることが必要です。
筋肉の活動は求心性収縮、遠心性収縮がありそれぞれ縮む方向、伸びる方向に活動するのが筋収縮です。
伸びるもしくは縮む方向へどちらの収縮であっても筋肉を動かす、伸び縮みできる範囲を広げることを優先します。
筋肉の硬さはストレッチのように伸ばすことが想像しやすいですが、筋肉を縮める(関節を曲げるなど)動きでも筋肉の長さは変化するので短縮を予防することはできます。
動かせる範囲を広げるためにストレッチという選択もありますが、ストレッチは筋緊張を低下させてしまうので刺激量には注意しながら行う事が大切です。
実際に筋肉を求心性(縮める)もしくは遠心性(伸びる)収縮させる方法は、「筋肉を押すか引っ張るか」です。
筋肉の収縮が生じるのは、体を動かそうとした時と重力や姿勢など無意識的な動きや動作でも見られますが、無意識な活動では神経活動を利用して筋活動を促していきます。
重力や自身の体の重さなどで、体の筋肉が押されたり部位によっては引っ張られ、その刺激に対して体は筋活動で支持して安定しています。
筋肉の繊維に沿って押す、引っ張ることで必ず押し返す、引っ張り返す作用が生まれます。(こういった体の反応があるので、無意識に立つことや歩くことが可能になります。)
この作用を利用することで、力任せに伸ばしたり、痛みを感じることは極端に軽減します。
痛みを伴う刺激は、体が拒絶・防御しようとしてかえって筋肉が硬くなる場合もあるので細心の注意が必要です。
〇筋肉の筋緊張が高い
筋緊張とは体を安定、動かすために必要な筋肉の張りです。
寝ている姿勢(安静姿勢)では、体がベッド面に支えられているので全身の筋緊張は低下します。
筋緊張が低下するといっても完全に脱力して、筋肉の張りが全くない状態ではなく絶え間なく24時間、重力と支持面へ適応するために、必要最低限の筋緊張を保ちながら生活しています。
この必要最低限ということが重要で、ベッドに寝ていても手足や腰、首などの緊張がコントロールされずに筋緊張が高い場合もあります。
これが脳卒中による筋緊張コントロールの障害の1つです。
筋肉の張り=筋緊張は高すぎても、低すぎても姿勢や動作へ影響を及ぼします。
リハビリで目指すべき筋緊張の正常は、高緊張↔低緊張といった上下をコントロールできることにあります。
筋緊張をコントロールできるためのリハビリはご自身の体や姿勢を無意識に感じ取れることが大切となり、自身の体の位置や長さといった感覚情報(無意識)がより正確に判断できることで、どの程度の緊張があれば姿勢を保てるのか、動かせるのかが認識できるようになります。
筋緊張に対してもストレッチが選択されることが多いですが、先ほどの短縮へのストレッチ以上に防御的な活動になりやすくより筋緊張を高める危険性があります。
筋緊張は脳が24時間、絶え間なくコントロールしており姿勢や運動に必要だと感知している結果なので姿勢や運動を安定させることが重要です。
寝ている姿勢であれば、背中や太ももの裏がベッド面にしっかりと接触して安定しているかなどを評価します。
ベッド面への接触が少なるなれば、不安定になるので必然的に筋緊張を高めて体を安定させようと活動してしまいます。
このような原理で座位や立位なども安定することで、必要最低限の筋緊張で体を動かすことができ歩行時の内反や肘の曲がりなどを軽減することに繋がります。
〇トリアのリハビリ相談

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。
公式LINE
https://lin.ee/DCXMsH0
こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください。

脳卒中や神経疾患等による症状の改善希望やご相談の方は、HPの情報をご参照ください。
〇さいごに
今回は筋肉の硬さを2つの要因から説明しました。
短縮、筋緊張ともにリハビリではストレッチが選択されやすいですが、脳・神経が拒絶せずに効果が持続するにはその背景にある原因へのアプローチが必要です。
体の硬さが気になる、動くと無意識に曲がってしまうなどの症状でお困りの際はお気軽にご相談ください。