トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ
TEL.047-711-3007
豆知識
子どもの発達に欠かせない遊び5選 理由と内容とは⁉
子どもの発達は、体力が落ちている事や運動量の減少などが指摘されていますが複合的な理由や遊び方の変化などによるものが影響しているのではないでしょうか?
タイトルの通り子どもの発達には、昔ながらの遊びがとても適しています。
昔から変わらずに伝わっているからこそ、楽しいだけではなく子ども達の発達を促すような内容になっています。
実際に療育などでも取り入れる場合も多く、そこにはしっかりとした理由があります。
この記事ではこちらの内容についてお伝えしていきます。
・昔の遊びを振り返ろう
・遊びの特徴を考える5選
・どの遊びにどんな子どもが適している?
ご家庭での遊びにも取り入れられるので、部分的にでも参考にしながらお子さんと遊んでみてください。
〇昔の遊びを振り返ろう
ふと、小さい頃の遊びっていつからあるの?誰が考えたの?と疑問に思うことがありました。
有名なケン・ケン・パを調べてみると日本では、諸説あるようで明治時代からあるようです。
イギリスの少女が考え、世界各国に広まり今でも多少違いはあるようですが世界中で遊ばれています。
他にも昔からある遊びで有名なものは、鬼ごっこや缶蹴り、だるまさんが転んだ、おしくらまんじゅうがあります。
昔から長く遊ばれ、今でも遊ばれている事には楽しいだけではなく、子どもの成長や発達に適したポイントがそれぞれあります。
〇遊びの特徴を考える 5選
それでは、ケンケンパ、鬼ごっこ、缶蹴り、だるまさんが転んだ、おしくらまんじゅうの5つを考えていきましょう。
①ケンケンパ

ケンケンパは、輪っかを置いたり地面に円を書いたりして、片足飛びや両足で飛ぶ遊びです。
そして最も重要なのは、飛ぶこともそうですがしっかりと着地することが発達においては大切です。
お子さんが自分の足で蹴って飛んで、その力をまた自分の足で受け止める、この繰り返しと片足や両足が組み合わさることで動きと安定という体の発達を育むことに繋がっていきます。
②鬼ごっこ

鬼ごっこにも単純に鬼役の子どもが、他の子ども達を追いかけてタッチする方法から〇〇鬼のようにいくつも種類があります。
・たか鬼
・こおり鬼
・いろ鬼
・かげ鬼
他にもあるかもしれませんが、これらの鬼ごっこはあるルールに従いながら追いかける、逃げる遊びです。
走ったり、登ったり、探したりと色々な事を考えながら遊ぶことだけではなく、ルールを守るという視点でもとても子どもの理解やルールを守るという考えを育むことができます。
③缶蹴り
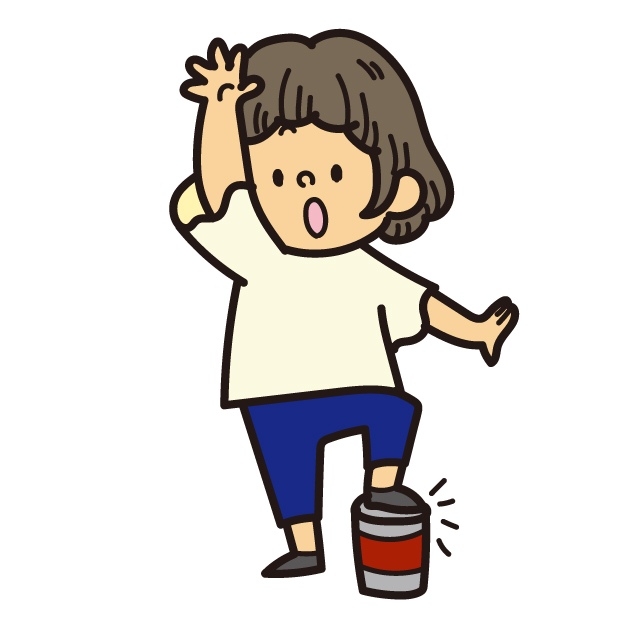
缶蹴りは簡単に言えば、鬼ごっこをしながら目標の缶を蹴る遊びです。
鬼ごっこと大きく異なるのは、逃げる側の子ども達、追いかける・捕まえる側の子ども達とのチーム戦になります。
どうやったら上手く捕まらずに缶を蹴れるのか、どう誘い出したら捕まえることができるのかなど時にはひとり一人で考え、時にはチームで話し合うことがあります。
こういった協力することやチーム意識などを育むことに長けています。
④だるまさんが転んだ

だるまさんが転んだの最大の特徴は、耳・聴覚を中心に目・視覚を使った遊びということです。
ここまで紹介した遊びは体を動かすことなどに長けていますが、だるまさんが転んだは耳で良く聞きながら走ったり、止まったりすることで話に集中することが繰り返し練習できます。
もちろん走ってから止まる動きもあるので、動きと静止を繰り返すことで姿勢を安定させるような効果も期待できます。
話に集中しながら体を動かすという、2つの課題を同時に行うような脳の働きを育むことができます。
⑤おしくらまんじゅう

おしくらまんじゅうは寒い時期に、背中やでお尻で押し合って体を温められるということで行われることもありますが、子ども同士で押し合うことで力の強弱をコントロールすることが練習できます。
どのくらいの力で、体のどの部位で押したらいいのかなど体の感覚を頼りに押し合うので、力の調整や体の感覚などを育むことに適しています。
〇どの遊びにどんな子が適している?
ここまで紹介した5つの遊びの特徴を踏まえて、どの遊びにどんあお子さんが適しているのか、やった方がいいのかなどをお伝えしていきます。
①ケンケンパ
「お子さんが自分の足で蹴って飛んで、その力をまた自分の足で受け止める、この繰り返しと片足や両足が組み合わさることで動きと安定という体の発達を育むことに繋がっていきます。」
上記の内容を含めて、輪っかに向かって飛ぶ、止まるを繰り返すので姿勢が不安定なお子さんや動きを切り替えることが苦手なお子さんに適しています。
低緊張や発達性協調運動障害(DCD)など指摘されたことにあるお子さんにおすすめで、最初はケンケンパのパを多めに設定してあげながら遊んでみてください。
低緊張による力の弱さなどはこちらの動画を参考にしてみてください。
パよりも片足のケンはバランスや姿勢を保つことが難しいので、ケンケンパのリズムでは出来ない、難しい、やりたくないが先行してしまうので難易度を少しずつ高めながら取り組んでみてください。
②鬼ごっこ
「走ったり、登ったり、探したりと色々な事を考えながら遊ぶことだけではなく、ルールを守るという視点でもとても子どもの理解やルールを守るという考えを育むことができます。」
お子さんとご両親のどちらか、もしくはご両親と2、3人では色々な鬼ごっこをすることは難しいですが、追いかける+1つのルールを作るという点だけを意識しましょう。
先ほどは記載していませんが、かげ鬼は二人でも遊べますし空間をここまでと決めてルールを作り遊ぶのも効果的です。
こういった鬼ごっこは、ルールを守る・意識することを育みたいということだけではなくルールを一緒に考える創造性を高めたいお子さんに適しています。
③缶蹴り
「どうやったら上手く捕まらずに缶を蹴れるのか、どう誘い出したら捕まえることができるのかなど時にはひとり一人で考え、時にはチームで話し合うことがあります。こういった協力することやチーム意識などを育むことに長けています。」
缶蹴りは他の子どもや大人の動きを観察することや、チームでの協力などが大切です。
大人数で出来ない時は、追いかけっこしながら何かに触るなど多少のルールを変えながらでも相手の動きを見る、観察するということはできます。
ひとり遊びではなく誰かと一緒に遊ぶことや、時間や空間を共有したい、育みたいという場合におすすめです。
④だるまさんが転んだ
「だるまさんが転んだは耳で良く聞きながら走ったり、止まったりすることで話に集中することが繰り返し練習できます。話に集中しながら体を動かすという、2つの課題を同時に行うような脳の働きを育むことができます。」
だるまさんが転んだは、体を動かす側面と話を聞くことが大切です。
歩いたり、走っていて転びやすいお子さんや姿勢を保つことが苦手な低緊張のお子さんなどにおすすめです。
また話を集中して聞くという点では、注意欠陥多動性症(ADHD)のお子さんのように話を集中して聞くことが苦手な場合にもとてもいい練習になります。
⑤おしくらまんじゅう
「どのくらいの力で、体のどの部位で押したらいいのかなど体の感覚を頼りに押し合うので、力の調整や体の感覚などを育むことに適しています。」
体で押し合うので姿勢が安定しづらいお子さんやいつも力が強くなってしまうお子さんなどに適しています。
また低緊張のように力を出しづらいなどのお子さんにもおすすめです。
押すことであれば手押し相撲やボールの押し合い、引っ張ることであれば綱引きなども非常に体の発達を促すことに長けています。
〇まとめ
今回は昔ながらの遊びについて、簡単な歴史や特化している部分、そしてどんなお子さんに適しているのかなどを紹介しました。
昔から残っている、遊ばれているものには魅力も理由もあります。
大人になってよく遊び方を考えると非常に理にかなっているものばかりです。
ぜひご家庭でも方法を多少変えてもいいと思いますので、遊びの中に取り入れてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
その他、発達に関する記事
・【発達の遅れ いつ?何で気付く?】 発達支援 療育
・【発達障害 発話や言葉の遅れ】コミュニケーション
・【子どもの発達】視野が狭い⁉発達に目の動きが重要
〇執筆・監修者情報
佐藤浩之:施設長
~経歴~
1991:千葉県生まれ
2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職
2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験
2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了
2022:トータルリハビリテーション トリアを開設
