トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ
TEL.047-711-3007
豆知識
【脳卒中 筋肉の硬さとは】個別性 短縮 筋緊張
脳卒中のリハビリにおいて筋肉の硬さは大きな課題です。
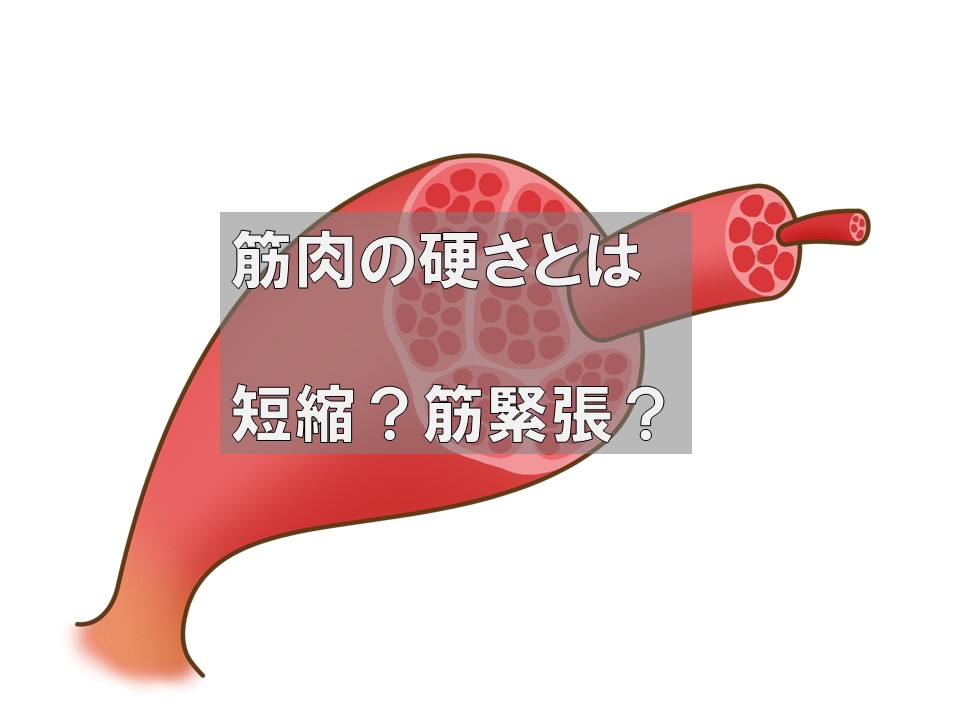
筋肉が硬くなると動かせる範囲が狭くなる、力がコントロールできないなどの症状へつながります。
しかし硬いといってもその原因や中身は人それぞれ異なり、症状に対して個別性を考えていく必要があります。
この記事では筋肉の硬さの原因について紹介していきます。
脳卒中後に肘が曲がってしまう症状にはこちらの自主リハビリ
無意識に関節が曲がってしまう場合は、感覚情報が重要になります。
〇個別性を高めたリハビリとは
個別性とは疾患ではなく、症状をみながら1人の患者様、ご利用者様を見ていくことにあります。脳卒中でいえば同じ出血部位、梗塞部位だとしても症状が同じではありません。
整形疾患においても筋力や体の使い方などで、リハビリ内容は大きく変わります。
どこまでその人らしさの背景を知り、生活に則したリハビリができるかが重要です。
〇脳卒中リハビリにおける筋の硬さの捉え方
脳卒中リハビリにおける個別性を考えるうえで、筋肉の硬さを捉えることは機能改善へ大きく関与します。
筋肉の硬さが生じる原因として大きく2つ
・筋肉の短縮
・筋緊張が亢進している
筋肉の短縮
筋肉の短縮とは、筋肉そのものが物理的に短くなっている状態です。
短縮は脳卒中を発症されすぐに生じるものではありません。
麻痺によって使いやすい筋肉とそうではなく筋肉があり、一定の動かし方や姿勢を続けることで筋肉の活動に偏りが出てきます。
これが筋肉の短縮が生じる原因の1つです。
そしてもう1つが筋緊張による短縮。
筋緊張が高く肘が常に曲がってしまう、指が曲がってしまうなどの症状が続くことで筋肉がその長さに固定され短縮が生じます。
この短縮を軽減させるには、筋肉の活動を求心性収縮から遠心性収縮へ切り替える必要があります。
短縮している筋肉は求心性収縮といって、筋繊維が縮まる方向への活動が高まっているので、遠心性収縮へ切り替えるためには適切な筋肉への感覚情報、刺激が必要になります。
ストレッチでも筋肉は伸びますが、ストレッチ後に筋肉は緩み弛緩状態になり力は入りづらくなります。
短縮している筋肉も力が入らなければいけないので、リハビリにおいてはストレッチではなく収縮の方法を切り替え柔らかくしつつ、力を発揮できる状態にすることが重要です。
筋緊張が亢進している
筋緊張とは筋肉の張りのことで、全身に筋緊張は存在します。
この筋緊張が姿勢や動きによって高まる、低くなることでスムーズな動きが可能になっています。
しかし脳卒中を発症されると発症直後は筋緊張が低下し、徐々に高くなってくるケースが多く筋緊張が高まりやすい部位が限定的になることで、筋肉の硬さとして表れます。
この筋緊張をコントロールするためには、姿勢の安定や非対称性の改善が重要です。
また運動時の筋緊張に関しては、運動の開始からどこで終わるのかなどを筋肉~脳へ伝えることが必要です。
当施設では筋緊張のコントロールを姿勢、運動からアプローチし脳からの運動指令を正しく筋肉に届けることを重要視しています。
〇さいごに
リハビリにおいて疾患特性を踏まえた内容は重要です。
ひとり一人のご利用者様の状態を把握し、適切な筋肉、脳へのアプローチをすることで退院後であっても機能改善の可能性はあります。
筋緊張や姿勢などへのアプローチを体験したことがない方は、ご相談からお気軽にお待ちしております。
最後までお読みいただきありがとうございました。
〇執筆・監修者情報
佐藤浩之:施設長
~経歴~
1991:千葉県生まれ
2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職
2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験
2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了
2022:トータルリハビリテーション トリアを開設
