トータルリハビリテーション

お電話での予約・お問い合わせ
TEL.047-711-3007
お知らせ
小脳性運動失調のリハビリ 小脳の機能と症状の原因
脳卒中後の後遺症には、失調、小脳性失調という症状があります。一般的にネットやSNS、教材などで失調を検索するとほとんどが小脳性運動失調が記載されいます。本来、失調とは身体、動作において協調的なコントロールが困難な場合を指し、小脳性以外にもいくつかの種類が存在します。
今回の記事では失調の種類の紹介と小脳性運動失調について詳しく解説していきたいと思います。
また身体を動かすことやコントロールする際には、小脳は非常に重要な脳部位でさまざまな機能を担っています。直接的な小脳の疾患だけではなく、他の脳部位での脳卒中であっても小脳へのアプローチが必要なケースもありますので脳卒中後の後遺症でお困りの方は参考にしてください。
小脳運動失調に関してはこちらの動画でも解説しています。
小脳性運動失調もしくは麻痺であっても失調の症状が混在している場合には、麻痺に対するリハビリ方法だけではなく失調の原因を理解したアプローチ方法が必要です。
〇目次
・失調の種類
・小脳性運動失調の症状
・小脳と運動機能の関連性とは?
・小脳性運動失調の各症状の原因とは?
・当施設での小脳性運動失調へのリハビリ場面
〇失調の種類
失調と言われる運動、動作における協調的なコントロールを阻害する原因は以下のような種類に分類されます。
・小脳性
・大脳基底核性
・感覚性/脊髄性
・前庭迷路性
・大脳性
脳卒中(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血)や外傷(交通事故など)、先天的(動静脈奇形)、腫瘍などにより各脳、神経部位の損傷によって引き起こされます。
脳卒中による症状は麻痺と言われる手足を動かす機能が阻害されることで一括りにされている事も多いですが、その中に失調、小脳性運動失調なども含まれています。
発症、損傷部位だけではなく実際の患者さんの状態や身体機能を療法士が見極める技術が求められます。
〇小脳性運動失調の症状
小脳出血、小脳周辺の梗塞などいくつかの要因によって小脳という脳部位自体の神経損傷によって小脳性運動失調が生じます。また小脳と密接に関連する脳部位(橋、視床など)で脳疾患が発症された場合にも小脳性運動失調が生じます。
小脳性運動失調にはいくつかの特徴的な症状があり以下のようなものが挙げられます。
1. 失調性歩行:足を広げてバランスをとる事や左右に揺れる、酔っ払ったような(酩酊歩行)歩き方になる
2. 四肢の協調運動障害:手足を動かすとき、狙った動きがうまくできない(測定障害)
3. 企図振戦:静止時には震えないが、動作中に手足が震える
4. 構音障害
5. 眼振:意図せず、眼球が左右に細かく動く
6. 姿勢やバランスの障害
7. 筋緊張の低下(低緊張):筋肉がだらんとした様に張りが少ない
8. 動作開始の遅れ(運動開始の障害)
症状の数が多く見えますが、根本的な原因から引き起こされています。
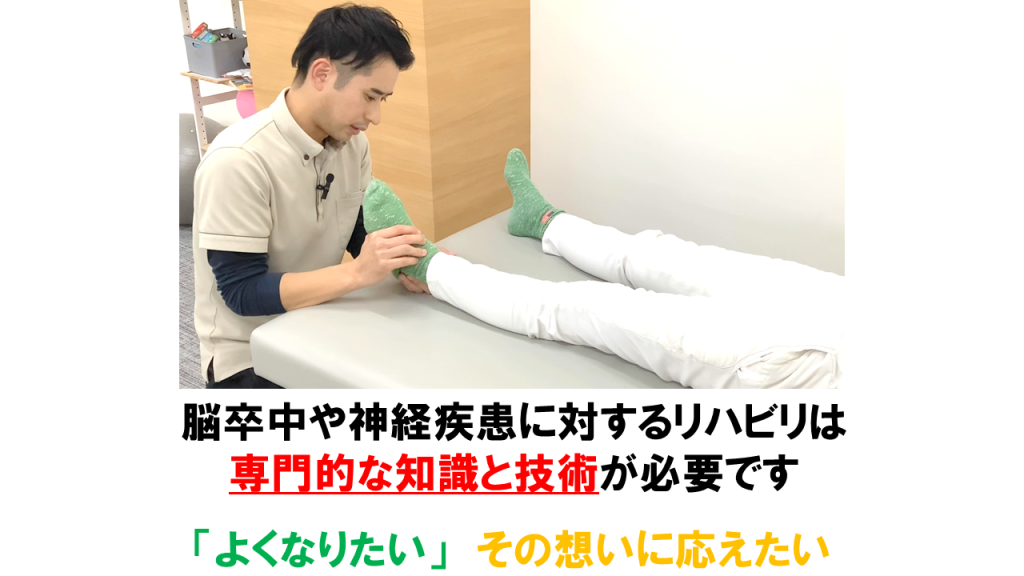
脳卒中の各症状の改善には、根本となる脳や神経系へのアプローチが重要です。
〇小脳と運動機能の関連性とは?
小脳の機能、特に運動に関する機能について解説していきます。
小脳が担っている運動機能は運動の質に関与するもので、運動の①強さ、②速さ、③方向をコントロールしています。他の脳部位の機能と大きく異なるのは、運動の質である強さ、速さ、方向は常にリアルタイムに修正、調整され続けています。
例えば目の前のコップを掴む際には、掴む前に見た目などの要素で記憶からおおよそこれくらいの重さだろうと予測した力加減で持ちますが、ここで重さと実際の力が合っていればそのままスムーズに持つことが可能です。この場面で実際のコップが予測より極端に軽いと、コップを勢いよく持ってしまうことになりますが、一定の位置でこの勢いは止まります。その背景には、小脳がリアルタイムに重さを感知してくれているので力の強弱などを瞬間的にコントロールできています。
今の例えは重さに対する力のコントロールで、先ほどの3つの運動の質である強さ、速さ、方向は常に重さに対して調整されています。では重さとは一体何を指すのでしょうか?
小脳がコントロールしている重さとは、物の重さを含めて重力や体の質量、抵抗感を指しています。抵抗感は物の抵抗だけではなく、筋肉の硬さも影響され筋肉は硬くなる、緊張が高くなることで伸びづらくなりますが、この伸びづらいということも1つの抵抗感になります。
これらの様々な重さに対して、常に運動の質をコントロールしいているのが小脳です。先ほどのコップの例は、そのまま小脳性運動失調の症状でもある手足の震えの原因、考え方に繋がっていきます。直接的な小脳疾患ではない患者さんの場合であっても、手足を動かしたい方向には動かせても途中で硬くなってしまうなどは小脳の機能が影響している可能性があります。

訪問リハビリについては、千葉県内や都内などまずはお気軽にお問い合わせください。
〇小脳性運動失調の各症状の原因とは?
小脳性運動失調の症状は、低緊張や手足や体が動作時に震える、歩行時のふらつき、声の大きさなど発声のコントロールが難しい、眼振などを挙げました。
また小脳は運動の質を全身の筋肉で調整しているので症状としても、手足だけではなく、目の筋肉や呼吸、発声に関わる全身の筋肉へ影響し協調的な動きが難しくなります。特に低緊張という筋肉の張りが低下していることが多く、この低緊張が安静時と運動時の筋緊張の差を大きくしてしまいます。これらの症状の原因、特に手足が動作時に震えてしまう症状の原因は先ほどのコップで例えた内容になりますが、コップの重さが自身の手足の重さに置き換えて考えていきます。
構音障害に関わる横隔膜や舌の機能についてこちら
→【脳卒中 構音障害と舌の動き】姿勢と横隔膜
例えばご自身の腕が10kgだと想像してみてください。座っている状態で腕を挙げると、この10kgを支えたり動かすだけの筋出力が必要で、力が弱くても強くても協調的な動きは難しくなります。実際に手足を動かす瞬間には、低緊張により体を支える力が出力されづらく本来の重さである10kgよりも重く感じてしまうことで動き始めに10kg以上の力で動き始めてしまいます。この動き過ぎてしまったという感覚情報に対して、出力がコントロールもしくは反対の出力を使って動き過ぎた腕を止めようとします。手を挙げる動きであれば下げる方向にわずかに出力しているということになります。しかし本来の腕を挙げる動作に対しては、反対方向になるのでこの反対の動きは運動に対する抵抗となり、さらにこの抵抗に負けないように腕を挙げる力を入れるので再度腕が揺れます。
動き始めから、力が入りすぎる→止めようとする→また力が入りすぎてしまう
この繰り返しによって手足が揺れています。その他にも筋の短縮や部分的な高緊張なども筋の抵抗感が強くなり重さとしての感覚情報になります。この動作時の揺れを軽減するためには、実際の手足の重さを正確に感じることや抵抗感の変化を捉えることが必要になります。
抵抗感は関節の動きや重力で、この2つを練習することが大切となりこちらの動画の後半部分で練習を紹介しています。
ご自身の体の重さや物の重さを正しく感じられることで、力の強さや速さ、方向などをコントロールしやすくなっていきます。
〇当施設での小脳性運動失調へのリハビリ場面
当施設で実施した小脳性運動失調の方へのリハビリ、改善動画はこちら
小脳性運動失調の症状はいくつも挙げましたが、関連する症状の原因や運動コントロールを理解することでリハビリのポイントを決めていきます。
〇トリアの公式LINE

当施設では日ごろの店舗でのリハビリや訪問リハビリ等に加えて、当事者の方や患者さんへの情報発信を行っております。本サイト上でのブログの更新、YouTube、各SNSなどを取り組む中でより患者さんが感じている疑問や不安などの声を聞く様になりました。その疑問などにお答えして、リハビリやご自宅での自主リハビリが良い方向へ進むようにトリアの公式LINEでリハビリ関する内容についてお伝えしています。
公式LINE
https://lin.ee/DCXMsH0
こちらのLINEでは、退院後に療法士と話す時間が無い・減った、症状の原因を知りたい、改善するには何をしたらいい?などの疑問やご質問にお答えしていますのでお気軽にご連絡ください!
〇まとめ
今回は失調の分類や小脳の機能、そして小脳性運動失調の症状や原因などを紹介していきました。
失調に揺れや重さを強い出力で止める・抑え込もうとすると、筋の短縮や部分的な高緊張になりさらに重さを強くしてしまうので重さを感じながら運動コントロールを高めていく必要があります。
〇執筆・監修者情報
佐藤浩之:施設長
~経歴~
1991:千葉県生まれ
2013:国家資格(理学療法士)を取得し、千葉県内の病院へ入職
2015:大手自費リハビリ施設へ入職し施設長を経験
2017:JBITA公認ボバース成人片麻痺基礎講習会修了
2022:トータルリハビリテーション トリアを開設
